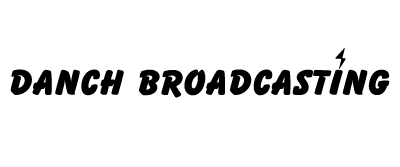不朽の名作『バンド・オブ・ザ・ナイト』で描かれた酩酊の世界

中島らもの最高傑作、『バンド・オブ・ザ・ナイト』。その中で描かれるジャンキーたちの悲喜劇は、逆説的にこの世界の歪さを浮き彫りにする。何度読んでも色褪せない本作の魅力を語り尽くす。
目次

『バンド・オブ・ザ・ナイト』は中島らもの最高傑作
『バンド・オブ・ザ・ナイト』は中島らものヘルハウス時代の話を描いた私小説。ヘルハウス時代とは、中島らもの家にジャンキー達が集まり、みんなで仲良くラリって生活していた時期である。
中島らもには数多くの名作があるが、『バンド・オブ・ザ・ナイト』はその中でも最高傑作であると思う。というのも、『バンド・オブ・ザ・ナイト』では、代表作の1つである『今夜、すべてのバーで』と異なり彼の内的思考は多くは語られない。しかし、本作で彼の思想・世界観は全て、ヘルハウス時代に体験したエピソードの羅列という形をとって表れる。披露されるエピソードの1つ1つが強烈なパンチラインとなっている『バンド・オブ・ザ・ナイト』の良さを言語化してみる。
まずは、勝手にあらすじを書いてみた。
あらすじ
大島英二(通称:ラム)、27歳。後先考えずに仕事を辞めた彼は、失業保険で食いつなぎながら昔やっていた「フーテン」に戻った。ラリるために睡眠薬を服用する彼の家には、やがて個性豊かなフーテン達が寄りつくようになる。ドラッグが出回ることから悪魔の家(ヘルハウス)と呼ばれるようになったラムの家で、フーテンたちは混沌と笑いに満ちた「クスリによるクスリのための生活」を送っていく。
ヘルハウスの住人のあふれる個性
『バンド・オブ・ザ・ナイト』には強烈な個性を持つ人物が多く登場する。しかし中でも、主人公・ラムの家の居候達、つまりヘルハウスの住人達はとびっきりの個性の塊である。『バンド・オブ・ザ・ナイト』の魅力を語る上で、ヘルハウスの住人達は欠かせない。ヘルハウスの住人達を、彼らの味がよく表れた文章の引用とともに紹介する。
ラムの嫁、”み”
“み”は主人公・ラムの嫁である。クスリに飢えたジャンキーが集まるヘルハウスにおいて、”み”が積極的にドラッグを求める描写は存在しない。他の住人達と比べるとかなり普通の人に見える”み”だが、彼女もまた頭のネジが外れている。それがよく表れた一節がこれだ。
みに豆腐を買ってきてくれ、と頼むと、みは、
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
「いいよ」
と言ってバイクで出かけた。そのまま三日間帰らなかった。我々はその間みが何をしていたのか、怖いので誰も訊かなかった。
主人公の昔からの友達、”エス”
エスはラムの古くからの友人で、180cmの大男。大男にも関わらず留学先のフランスでセネガル人にレイプされた悲しい過去を持っている。歴の長いジャンキーで、ラリると攻撃的になりいつもトラブルを起こす。エスはカフェで知り合った人間をいつもラムの家に連れてくるのだが、彼のこの習性とラムの「来るもの拒まず」な姿勢がヘルハウスの混沌を形作っていく。
エスにはタームスで知り合った誰それをおれの家に連れてくるという、ある種の昆虫じみた癖があった。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
アル中でヤク中のオーストラリア人、”ショーン”
エスに連れられてヘルハウスの住人になったオーストラリア人で、ウォッカとドラッグが大好物。自称アーティストだが、酒とドラッグばかりで何かを製作している様子は一切ない。
ショーンは睡眠薬とアルコール中毒で、一日にウォッカを一本半くらい飲んだ。身体がでかいから持つのかもしれないが、それにしても、
「やり過ぎだよ」
とおれがいうと、ショーンはウォッカをらっぱ飲みしながら、
「ノー・プロブレム」
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
と答えるのだった。ほんとうはショーンはプロブレムだらけだった。
ショーンの恋人、”コッケ”
コッケは酒も飲めず、タバコも吸えない。そんな彼女は酩酊を得る手段としてドラッグを選ぶ。
コッケは酒が飲めない睡眠薬中毒者で、年は二十八だった。家に一台だけあるリクライニング・チェアに身体を預けて、一日中とろとろと眠っていた。その姿は半眼微笑のホトケさまのようだった。ときどき目覚めて菓子を少し食う。食事らしい食事をしているのは見たことがなかった。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
分裂病者でパンクスの”ガド君”
ガド君はモヒカン頭の精神分裂病者。口癖は「ダメだっ」。ペグが1個なくなった五弦ギターをいつも持ち歩いているが、「ずっとノイズでやってきた」ためコードが弾けない。
ガド君はどうも悪い電波が来るようでしきりに、
「ダメだっ」
を連発していた。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
京大出身の万引き常習犯”岡本さん”
岡本さんは本屋での万引きと地図屋のアルバイトで生計を立てるヤク中。物語開始時ですでに3カ月も居候している。妙に丁寧な口調で話し、博学に見えるが彼の意見は全て本の受け売りである。
仕事にも万引きにも行かない日は、うちで終日ラリっている。うちの居候になって、もう三カ月近くになる。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
なんでもパクる、ノン・ジャンル万引き野郎”ケンちゃん”
本屋での万引きを主とする岡本さんとは異なり、ケンちゃんはオールジャンルで万引きをする上、よく警察に捕まる。好きな作家は三島由紀夫だが、実はIQが70しかない。
「今ね、三島を読んでるんだよ」
とケンちゃんが言った。おれは、
「ふうん。おれは三島を読んだことがないんだよ。あ、『仮面の告白』は読んだけど」
「ラム君、三島は読まなくちゃだめだよ、三島は」
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
お察しの通り、いわゆる”マトモ”な人は1人も登場しない。しかし、ヘルハウスの中では”マトモ”でないことはマジョリティである。”マトモ”でない彼らが、自分に素直に生きている様を見ると、”マトモ”に生きている方が不自然なのではないか、という気持ちになる。
酩酊を言語化した言葉の濁流
『バンド・オブ・ザ・ナイト』はクスリが大好きなジャンキー達の物語で、物語の語り手であるラムも例に漏れずヤク中である。そのため、物語の中では時々「ラリっている」シーンがある。時々といっても全部で7回、計130ページくらいラリっている。そしてそのラリっている状態は、『バンド・オブ・ザ・ナイト』の中では言葉の羅列という形で表現される。百聞は一見にしかずだ。引用しよう。
いくつかの言葉が嵐のように脳裡を過ぎ去っていく。
その言葉は誰のものでもない言葉。砂の王国の市を行きかう言葉。日照りの灼熱の下でひからびていく言葉。
そしてその言語が囲繞できる猫の額ほどの土地とショウジョウバエで真っ黒になったミルクティのコップと、未だ名づけられないさまざまの感情と包茎の先のピアスと誰に言うでもないさようなら、大事なセリフを吹き飛ばされて子供みたいに吹き飛ぶT字路、そうお前の匂いのする街でとてもシラフじゃいられない、マラリアにかかった赤い月、呪言、水のような下痢、カルカッタの乞食、未封のメンソレータム、”あっ”と”それで?”「私がいつ」と「時間よとまれ」と「いつの日にかね」が交差するスクランブル・エリア、……
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
そう、訳がわからないのである。しかし、実は全てがでたらめに訳がわからないと言うわけでもなく、わかりやすい部分もあるのだ。例えば首狩りママだ。首狩りママについて述べている部分は文章の体をなしていて、とても読みやすい。
首狩りママは考える。なぜ世界は牛の糞でできているのか。なぜ排水溝は小便で一杯でときどき胎児が流れてくるのか。なぜ影は実態の一部であることを主張しないのか。なぜ人々はアイデンティティという幻想に憑かれるのか、なぜ猫は愛情の過多のためにカーペットの上でゲロを吐くのか、なぜ女はタマネギを刻むときにだけ本当の涙を流すのか。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
(中略)
首狩りママは考える。彼女の脳は胡桃くらいの大きさしかない。それでも首狩りママは考える。…
この言葉の濁流は、ある種この世界への挑戦なのではないかと思う。多くの人は『バンド・オブ・ザ・ナイト』を読んでいて、この言葉の濁流に直面した時、眉をしかめるだろう。それはこの言葉の濁流が我々の認識できる範囲を超えていて、「意味がない」もしくは「意味がわからない」と感じるからだ。ナンセンスであることは悪だろうか?
仕事、勉強、恋愛、バリュー、クリエイティブ……我々は普段「意味のある」日常を生きているため、一見「意味がない」「意味がわからない」ことに対して耐性がないし、そうしたものを嫌う。一方、『バンド・オブ・ザ・ナイト』ではこうした言葉の濁流と、ジャンキー達の「意味のない」行動の連続で物語が進む。「意味がないものアレルギー」な我々に、中島らもは「意味あることが正しいのだろうか。本当にそうだろうか」と疑問を投げかけていたのかもしれない。
そもそも、この言葉の濁流の意味を解釈することを彼は求めていないように思う。その証拠に、『バンド・オブ・ザ・ナイト』はこんな引用から始まっている。
歌詞なんて聞き取れる必要はないんだよ。
ロックの場合はね。
ルー・リード
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
「ロックの英語歌詞なんて聞き取れる必要はない」というのは中島らもが様々な著作で述べていることだが、ここでの意味合いは少し違う。歌詞とは言葉の濁流、ロックとは『バンド・オブ・ザ・ナイト』そのもののことではないだろうか。
意味なんて考えず、黙って感じろ。と言われている気がする。
『バンド・オブ・ザ・ナイト』から世界を見直す
『バンド・オブ・ザ・ナイト』にはラリっている描写がたくさんあることは先ほど述べた通りだが、そもそもラリるとはどういうことだろう。
ラリるとは、我々が素面で生きている世界を「理性の世界」としたときに、真逆の原始的な「感覚の世界」に一時的にトぶことだと思う。体は「理性の世界」から離れることができないが、意識だけは「感覚の世界」へトぶことができる。「感覚の世界」では、五感で感じたままにしか動けず、行動に頭脳は介在しない。本能としてしたいことをただするのである。
時々、人間はそれでいいんじゃないかと思う時がある。一度「感覚の世界」を知ってしまうと、きれいさっぱり忘れ去ることはできない。「感覚の世界」を一度知ってしまった意識は、「理性の世界」でしか生きれない体にはうまく馴染めない。
『バンド・オブ・ザ・ナイト』は、そんな「理性の世界」に馴染めなくなったヤツらの物語だ。ガド君の訃報が届いたシーンに、それを象徴する一節がある。
エスはうちにきてクスリをがりがりかじりながら言った。
「ガド君はね、この世に向いてない人だったんだよ。そう思わないか」
そう思う、とおれは答えた。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年
「理性の世界」が当たり前のようになってしまっているけれど、「理性の世界」は実はとっても不自然で、本当はそんなものに縛られず気ままに生きた方がいいのかもしれない。そんなことを考えさせられる。
町田康が付け足す後味
『バンド・オブ・ザ・ナイト』は本編だけでなく、解説までを含めてひとつの作品だと言える。それは、本の最後にある町田康の解説があまりにも的確で、情緒があり素晴らしいからだ。本編を読んで、一息ついた後はぜひ解説も読んでみてほしい。もう一度読み返したくなるハズだ。
最後に、そんな素晴らしい解説からの一文で締めようと思う。
私は世界にはここに書いてあること以外なにもないし、ここに書いてあること以外、なにも必要ないと思った。
中島らも『バンド・オブ・ザ・ナイト』講談社、2000年