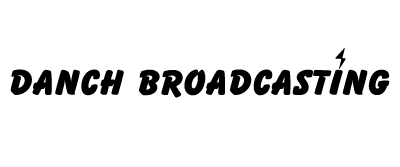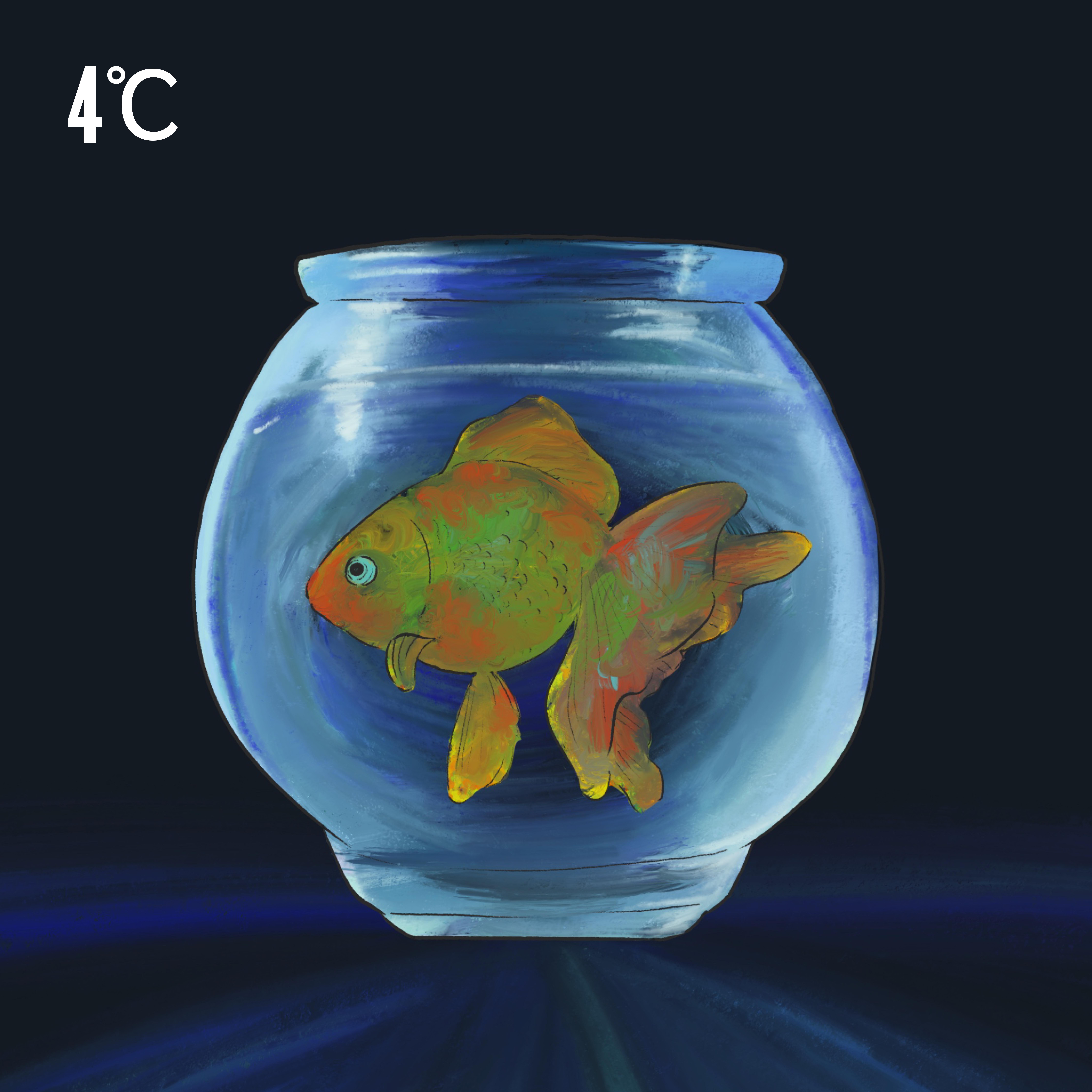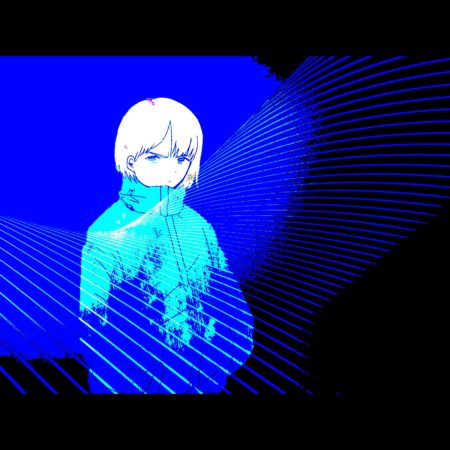酒を片手に、文章に酔う。『今夜、すべてのバーで』の味わい方

中島らもの代表作である『今夜、すべてのバーで』。彼の美しい文章と深い内的思考は、読む私たちを陶酔させる。”アル中”を皮切りに人間の依存、中毒の本質に迫った本作で、彼は何を伝えたかったのだろうか。
目次

『今夜、すべてのバーで』でらもの世界観に浸る
中島らもの代表作、『今夜、すべてのバーで』は彼が連続飲酒の末倒れた時の、入院から退院までの体験をベースにした私小説だ。もしあなたが中島らも作品に少しでも興味を持っているのなら、是非最初に手に取ってみてほしい。
というのも、ドラッグを中心に話が進む『バンド・オブ・ザ・ナイト』など他の著作と比べ、本作は「アルコール」という私たちにとって身近なものを中心に話が進む。そのため、中島らもを全く知らない人でも彼の世界観に浸りやすい一冊であると言えるだろう。
今回は、そんな『今夜、すべてのバーで』の魅力を余すことなく紹介する。
まずは、勝手にあらすじを書いてみる。
あらすじ
医者、占い師、昔の友人という3人の人間に「三十五歳で死ぬ」ことを予言された男、小島 容(こじま いるる)は、その予言通り飲酒が原因で三十五歳で倒れ、入院することになる。アル中文献を肴に酒を飲み、誰よりも「アル中」に詳しくなったアル中は、酒から切り離された有り余る時間の中で自分の人生と死、そして依存について考える。
酒にまつわるお洒落な引用
『今夜、すべてのバーで』の魅力の一つが、酒にまつわる引用の数々である。”酒”に焦点を当てた本作は、こんなエジプトの小話からの引用で始まっている。
「なぜそんなに飲むのだ」
「忘れるためさ」
「なにを忘れたいのだ」
「……。忘れたよ、そんなことは。」(古代エジプトの小話)
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
中島らも作品には軽快なジョークが多い。一見ジョークに見えるこの引用が、読む前から私たちに本作のテーマである「薬理としてのアルコール」について考えさせる。
物語の終盤では中国・唐代の詩人、于武陵の『勧酒』について触れられている。『勧酒』は簡単にまとめると、友人との別れを惜しみ「人生に別れはつきもので、いつ何時本当の別れがくるかわからない。今を大事にしよう。」という意味の漢詩だ。本作では井伏鱒二の訳が引用されており、将来よりも「今」を生きる刹那主義の歌として描かれている。
この盃を受けてくれ
どうぞなみなみつがしておくれ
花に嵐のたとえもあるぞ
さよならだけが人生だ
ってな
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
入院により酒を絶っている主人公・小島容に、同じ病室の福来益三という登場人物がこの言葉を発する。福来は小島に、好きな酒をなんのために我慢するのか、好きな時に好きなだけ飲む生き方が正なのではないかという問いを酒とともに突きつける。そのシーンで誰もが知っている有名な『勧酒』を持ってくる中島らものセンスに脱帽する。
中島らもを代弁する登場人物
『今夜、すべてのバーで』には様々な登場人物が出てくるが、話の本筋に密接に絡んでくるのは4人だといえる。主人公の<小島容>、主治医の<赤河>、同じ病室のアル中・<福来>、死んだ旧友の妹・<天童寺さやか>の4人だ。本作は私小説で、主人公の「中島らも=小島容」として読む読み方は確かに正しい。しかし、中島らもの他のエッセイと比べて読むと、前述の4人の登場人物はそれぞれ別の点で中島らもを反映していることがわかる。
中島らもの思想を体現する”小島容”
『今夜、すべてのバーで』が実体験を基にした私小説である以上、主人公である小島容が中島らもを代弁しているのは言わずもがなである。中島らもは主人公・小島容を通して内的思考を描き、彼のパーソナリティの輪郭を私たちに伝えてくれる。例えば、次の部分である。
その頃のおれには、貧しいがゆえのプライドのようなものがあった。自分は”特別な人間”だという意識。世に容れられず、また力の試し方を知らないために余計に狂おしくつのっていく自分の才能への過信、不安、その両方が胸の奥で黒く渦巻いていた。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
三十まで転がって暮らしてきたおれには、守るもの、失って困るものはなにもなかった。守りたいのは形のない、他人に言ってもわからないものばかりなのだ。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
中島らもの自意識と自己嫌悪、苦悩などがありありと目に浮かぶ。中島らもの魅力の一つに文章の美しさがあるが、彼の内的思考を描いている部分にも、その美しさが際立つ一節があるので紹介したい。
内臓は頑丈でも、おれの心には穴がいくつもあいていた。夜ごと飲みくだすウイスキーは、心にあいたその穴からことごとく漏れてこぼれ落ちてしまうのだった。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
刹那主義で誘惑するもう一人の自分、”福来益三”
福来益三は小島と同室に入院しており、その原因は小島と同じ飲酒だ。しかし、彼は主治医である赤河に隠れて酒を飲み、入院するごとに下りる保険料で暮らしている。そんな福来はアル中は治らないと断言し、将来のために今我慢することの無意味さを説く。
主人公・小島は「飲むことと飲まないこと」は「具体と抽象」の戦いである、としている。ここでは「具体」とは目の前にある欲望、「抽象」とは未来のボンヤリとした幸福を指している。つまり、酒をやめるためには、飲むことによって得られる快感という「具体」を、生への執着や他者への愛という「抽象」が上回らなければならないということだ。入院によって物理的に酒と切り離された小島は「具体」と「抽象」の間で揺れる。そこで福来は小島の眼前に「具体」をつきつけるのだ。これは中島らもの中で常に自分に向けられていた甘言そのものなのだと思う。
今の日本じゃ、酒は水か空気みたいなもんだ。どこへ行っても目の前にあるんだ。そんなところで断酒なんかができるかね。十二年断酒したあげくによけいみじめになるくらいなら、私は飲むよ。死にかけの体の機嫌をとりながらね。私は酔ってる時だけが、生きてるときなんだから。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
“赤河先生”が代弁する自己嫌悪ともうひとつの人生観
主人公・小島の主治医、赤河はぶっきらぼうで、飲酒で自ら死に向かうアル中を毛嫌いしている。赤河はアル中治療について意見する小島に向かってこう言い放つ。
どうも私には鼻持ちならんのだよ。はっきり言うとね。たとえば、あんたは自分と他のアル中を比べてみて、どうだ。自分はなにか特別にデリケートで、特別に傷つきやすくて、そのせいでアルコールに逃げたんだ、とか、そういう薄気味悪いことを考えてるんじゃないのか。自分だけが、言やあ、天に選ばれしアル中、みたいな。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
この一節は、小島の自意識の高さを言い当て、痛いところを突いている。自分自身の自意識に対する自己嫌悪みたいなものを、赤河に代弁させているのかもしれない。また、赤河は17歳で病気で亡くなった少年の死について次のように語っている。
大人にならずに死ぬなんて、つまらんじゃないか。せめて恋人を抱いて、もうこのまま死んでもかまわないっていうような夜があって。天の一番高いところからこの世を見おろすような一夜があって。死ぬならそれからでいいじゃないか。そうだろ。ちがうかい?
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これは中島らもが常々考えていたことのように思えてならない。小島容と赤河という2人の登場人物を通して、自分の中にある様々な死生観を読者に示しているといえるだろう。
取り残された側の意見を代弁する”天童寺さやか”
天童寺さやかは、小島容の秘書かつ旧友・天童寺不二雄の妹として登場する。天童寺不二雄は破天荒な人生を歩んだ末、さやかを残して交通事故で死亡した。
連続飲酒で自ら死へ向かう小島に対して語る、さやかの思いは中島らもの「死者に取り残された側」としての意見を代弁し、彼の死生観の片鱗を見せてくれる。さやかが語った言葉はこうだ。
思い出になっちゃえば、もう傷つくことも、人から笑われるような失敗をすることもない。思い出になって、人を支配しようとしているんだわ
(中略)
死者は卑怯なのよ。だからあたしは死んだ人をがっかりさせてやるの。思い出したりしてあげない。心の中から追い出して、きれいに忘れ去ってやるの。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これに似たことを、中島らもは彼のエッセイ『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』でも語っている。浪人時代に自殺した友人に対して述べている一節だ。
自分だけすっぽり夭折するとはずるいやつだ、と僕は思う。薄汚れたこの世界に住み暮らして、年々薄汚れていく身としては、先に死んでしまった人間に嘲笑されているような気になることもある。
中島らも『僕に踏まれた町と僕が踏まれた町』集英社、1997年
この経験が、前述のさやかの発言に繋がっているのだろう。引用部より後の部分もとても美しい文章なのだが、それはまた別の機会に紹介する。『今夜、すべてのバーで』は傑作だが、他作品と並べて味わうことでより味わい深くなる。
中島らもが伝えたかったこと
作中に中島らもが本作を通じて伝えたかったことが表れている一節がある。
薬物中毒はもちろんのこと、ワーカホリックまで含めて、人間の”依存”ってことの本質がわからないと、アル中はわからない。わかるのは付随的なことばかりでしょう。”依存”ってのはね、つまりは人間そのもののことでもあるんだ。何かに依存していない人間がいるとしたら、それは死者だけですよ。いや、幽霊が出ることを見たら、死者だって何かに依存しているのかもしれない。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これはまさしく中島らもが『今夜、すべてのバーで』で伝えたかったことであると感じる。アルコールに対する依存を中心に話が進むが、結局人は何かしらに依存して生きている。それは「酒」であれ、「タバコ」であれ、「ドラッグ」であれ、「恋人」であれ、「趣味」であれ、「権力」であれ、「名誉」であれ、依存の本質は一緒だということだ。つまり、アル中やヤク中、タバコをやめられない喫煙者はもはや誰にとっても他人事ではない。自分の依存と自覚して向き合い、上手く付き合っていくことが大切だ。
『今夜、すべてのバーで』名言とパンチライン
中島らもの作品にはたくさん名文がある。これをパンチラインと呼ぼうと思う。記事の最後に、『今夜、すべてのバーで』のベストパンチラインを3つ紹介したい。
おそらくは百年たってから今の日本の法律や現状を研究する人は、理不尽さに首をひねるにちがいない。タバコや酒を巨大メディアをあげて広告する一方で、マリファナを禁じて、年間大量の人間を犯罪者に仕立てている。昔のヨーロッパではコーヒーを禁制にして、違反者をギロチンにかけた奴がいたが、それに似たナンセンスだ。まあ、いつの時代も国家や権力のやることはデタラメだ。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これはドラッグや大麻に関して中島らもが終生貫いていた価値観だ。この価値観を貫いた結果、彼は大麻取締法違反で逮捕された後、裁判の際に独自の「大麻解禁論」を唱えたという。他作品にも通ずる価値観なので、ここに書かせてもらった。
酔生夢死か、いがらっぽくても生きる方を選ぶか。赤いマントか青いマントか。こいつは実に重大な問題だ。考え出したら一生かかるような難問だ。誰かおれのかわりに考えてくれないだろうか。そして、お前は赤マントだ、といった結論だけを命令してほしい。なぜそうなのか、の理屈はいらない。おれはヘソ曲がりだから、誰かが命令してくれればそれに逆らうことができる。それでやっとどっちかへ転がり動いていける。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これは全国スケールで語り継がれる怪談「赤マントと青マント」を使って彼の世界観を表現した一節である。この怪談は女に「赤マントをかけてあげようか、青マントをかけてあげようか」と聞かれ、赤マントと答えると血だらけになって死に、青マントと答えると全身の血を抜かれて死ぬというものだ。
どちらを選んでもしんどい結果が待っていることを、「酒を飲んでさっぱり死んでしまうか、酒を断って現実と向き合い生きていくか」ということと重ねている。どちらも選べない優柔不断な自分と、誰のいいなりにもなりたくないへそ曲がりな自分を同時に表現している名文だと思う。
人間はそれでいいのではないか。名前すらなく、飲んで飲んで飲みまくったあげく目詰まりのした「アルコール濾過器」として、よく燃えて骨も残さない、きれいさっぱりとした「具体」であって何がいけないのか。どうして人はアル中であってはいけないのか。えらそうな「人間」でなくてはならないのか。俺は自分の中で、中学生がやるような自問自答をくりかえす。
中島らも『今夜、すべてのバーで』講談社、1994年
これは疑問を投げかけていると同時に、自分の生きる意味を探している葛藤を描いている一節だと思う。自分に「アルコール濾過器」以上の価値があるとしたら、それは何なのか。なぜ、煩わしいことを考えて生き続けなければならないのか。
中島らもは階段から落ちて2004年に急逝したが、自殺はしなかった。彼なりに生き続ける意味を見出した結果だったのだろう。この問いかけは私たち全員のアイデンティティに直結している。私たち一人一人の生きる意味は何なのか。答えが出る日は来るのだろうか。