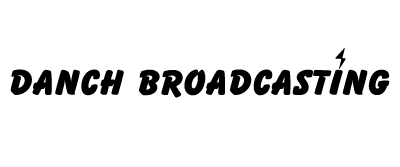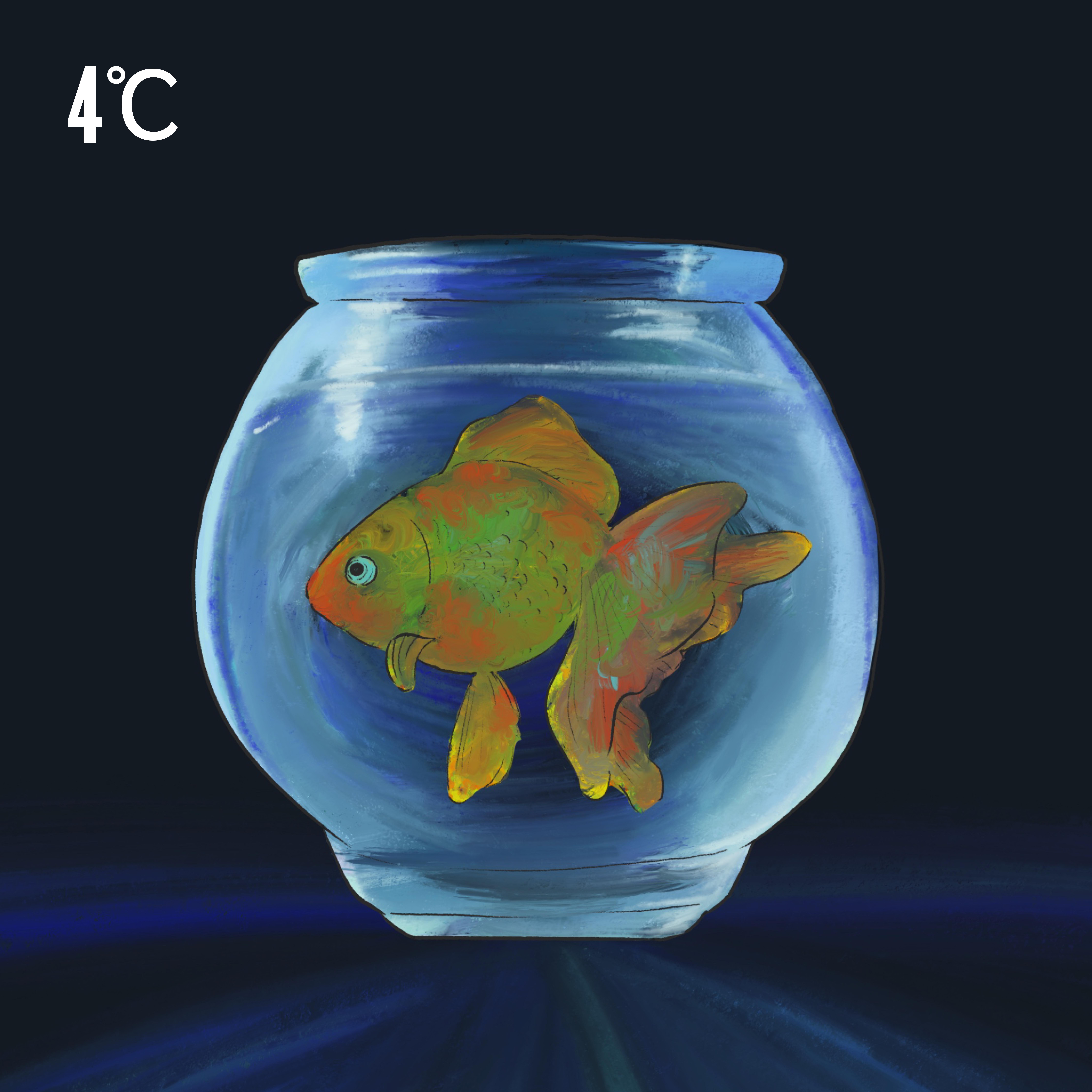『コンビニ人間』が映し出す”普通”であることの不自然さ

2016年に芥川賞を受賞した村田沙耶香の小説、『コンビニ人間』。18年間コンビニでアルバイトを続ける「普通」ではない「私」の視点を通すと、「普通」な世界は不思議に見える。「普通」なはずの私たちに疑問を投げかける奇作から、私たちの「普通」を考え直してみる。
目次

『コンビニ人間』とは
『コンビニ人間』は18年間コンビニでアルバイトを続ける「普通」が分からない女性を主人公とした小説だ。そして、そんな主人公がコンビニのアルバイトにこだわるのには理由がある。
朝になれば、また私は店員になり、世界の歯車になれる。そのことだけが、私を正常な人間にしているのだった。
村田沙耶香『コンビニ人間』文藝春秋、2016年
その理由とは、完璧なマニュアルと「こうあるべき」というハッキリした像がある「コンビニ店員」である間は、マニュアルに従って理想とされる像を演じることで社会の一部になれるというものだ。そしてそんな普通じゃない主人公、「私」の視点で物語は語られる。
「私」の周りには何気ない日常しか出てこない。しかし、『コンビニ人間』はそんなありふれたはずの日常を、普通でない「私」の視点と内的思考を通して語ることで、「普通」であるはずの私たちに「普通とは何か?」という疑問を投げかける。その答えを考えてみよう。
まず、最初に軽くあらすじを書いてみる。
あらすじ
コンビニバイト歴18年の36歳、古倉恵子は「普通」なことがわからない。そんな「普通」ではない彼女は、コンビニで働いている間だけ「コンビニ店員」として社会に受け入れられる。しかし、18年間コンビニ店員として働き続け、恋人もおらず正社員でもない彼女は、次第にコンビニの中でも「普通」でなくなっていることに気がつく。
変わらないものについて
『コンビニ人間』内にとても印象的な一節がある。「私」と常連の女性客とのやりとりだ。
女性は目を細めて言った。
村田沙耶香『コンビニ人間』文藝春秋、2016年
「ここは変わらないわねえ」
私は少しの間のあと、
「そうですね!」
と返した。
店長も、店員も、割り箸も、スプーンも、制服も、小銭も、バーコードを通した牛乳も卵も、それを入れるビニール袋も、オープンした当初のものはもうほとんど店にない。ずっとあるけれど、少しずつ入れ替わっている。
それが「変わらない」ということなのかもしれない。
客は「私」の働くコンビニのことを「変わらない」というが、年月を経てコンビニの中の人も物も入れ替わっており、確実に「変わって」いる。というか、時間の経過によって変わらないものなどどこにもない。でも、これは客の頭がおかしいわけじゃないことは万人が理解できるだろう。
では、何を以って客は「変わらない」と言ったのだろう。私たちはなぜそれに共感できてしまうのだろう。
“自分にとって”の「変わらない」
上記の会話で、客が「変わらない」と言ったのは、客にとってのコンビニが「変わらない」という意味だ。噛み砕くなら、今も昔もコンビニが同じ場所にあって、同じ時間に営業していて、大体同じだけの従業員数と客数がいる。客がそのコンビニに求める役割を、今も昔も変わらず果たしている。「変わらない」とはその程度の意味だ。変わってないものなんてどこにもない。
理解できないことに対する想像力
「変わらない」の話に代表されるように、仕方のないことだが、人は自分主体でしかものが考えられない。そして、それを時々無意識のうちに他人に押し付けてしまうことがある。『コンビニ人間』で、「私」が恋愛をしたことがないと言ったときに、周りが勝手な思い込みで話を進めるシーンを引用しよう。
性に無頓着なだけで、特に悩んだことはなかったが、皆、私が苦しんでいるということを前提に話をどんどん進めている。たとえ本当にそうだとしても、皆が言うようなわかりやすい形の苦悩とは限らないのに、誰もそこまで考えようとしない。そのほうが自分たちにとってわかりやすいからそういうことにしたい、と言われている気がした。
村田沙耶香『コンビニ人間』文藝春秋、2016年
主観で物事を考えるのは悪いことではない。むしろ、主観でしか物事は考えられない。しかし、相手が自分と同じような感覚を持っているとは限らないので、相手は自分が理解し得ない考えを持っているかもしれない、という想像力は常に持っておいた方がいいのかもしれない。
みんな自分が理解できないことが嫌いだ。けれど、世の中自分の頭で理解できることばかりではないので、理解できないこともあるという事実を受け入れると少し受け入れられることが多くなる気がする。
「普通」と共通前提
『コンビニ人間』の主人公である「私」は、周囲の「当たり前」に共感できない。周りが腹を立てていることも、「私」の恋愛経験のなさに同情していることも、頭では理解していてもそれに共感することはない。
ここで「私」と周囲の人々の決定的な違いは実は「共通前提の有無」でしかない。周囲の人間は「恋愛は皆したいものだ」とか、「仕事に不真面目なのはいけないことだ」とか、そういった共通前提を暗黙のうちに共有している一方、「私」はその前提を持っていない。これだけだ。
『コンビニ人間』における「私」と周囲の共通前提のズレは確かに大きいものだが、小さいズレは私たちの周りにいくらでも存在している。大げさに描かれているから、共通前提を持たない「私」が異質に見えるだけだ。
「普通」とは何か?
前述のように、「普通」とは共通前提によって定義される。「高校は通うものだ」とか、そういったものだ。高校は義務教育ではないため通う必要はないが、一億総中流社会を経て高校進学は「共通前提」となった。
マスの時代が終わり、人々が自分の好きな情報にだけアクセスするようになった今、人が趣味嗜好は多様になった。人が皆別々の情報を浴びて生活するようになると、こうした「共通前提」は揺らいでくる。観る動画、聴く音楽、ニュースの情報源、接触するSNS…これら全てが違えば「当たり前」は人によって当然異なる。
そうしたときに、「普通」という概念はもはや意味を持たないのかもしれない。「普通」な人々が共有する共通前提を表す言葉に「常識」があるが、「常」に同じものなんてない。全ては変化していく。
だから、「常識」だとか「普通」というのは、実は存在しない。常識を語る人がいたとしたら、それは「その人の中では、そういうことになっている」というだけの話だ。
コンビニ人間は特別か?
普通と共通前提について書いたが、『コンビニ人間』の主人公である「私」は特別なのだろうか。たしかに周囲との共通前提との大きなズレがあるという意味では特別だが、共通前提が揺らぎつつある今、「周りと違う」というのはもはや特別なことではない。それは『コンビニ人間』の文章にも表れている。
『コンビニ人間』の中で、詳細な人物描写はあまり出てこない。主人公である「私」に関しても、年齢と性別とあまり可愛くはないことくらいしか描写がない。これは、「私」や周囲の人々の描写をぼかして読者の想像に任せることで、「誰の周りにも起こりうることだ」ということを暗に示しているのではないかと感じる。
正常な世界はとても強引だから、異物は静かに削除される。まっとうでない人間は処理されていく。
村田沙耶香『コンビニ人間』文藝春秋、2016年
最後に
共通前提がゆらぎつつあるが、人は他者との共通前提なしでは生きられない。土地や情報に紐づけられた共通前提が壊れているなら、新しい共通前提を作るしかない。
この時、ダンチブロードキャスティングが目指すカルチャーによる共同体は、感性に紐づけられた新しい共通前提を作るのに一役買うかもしれない。そんな時代がやってきたらいいのに。