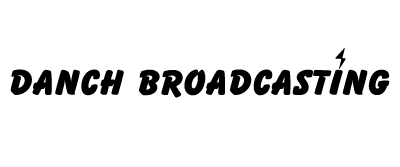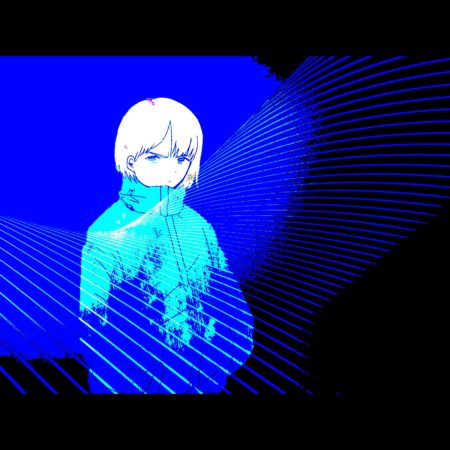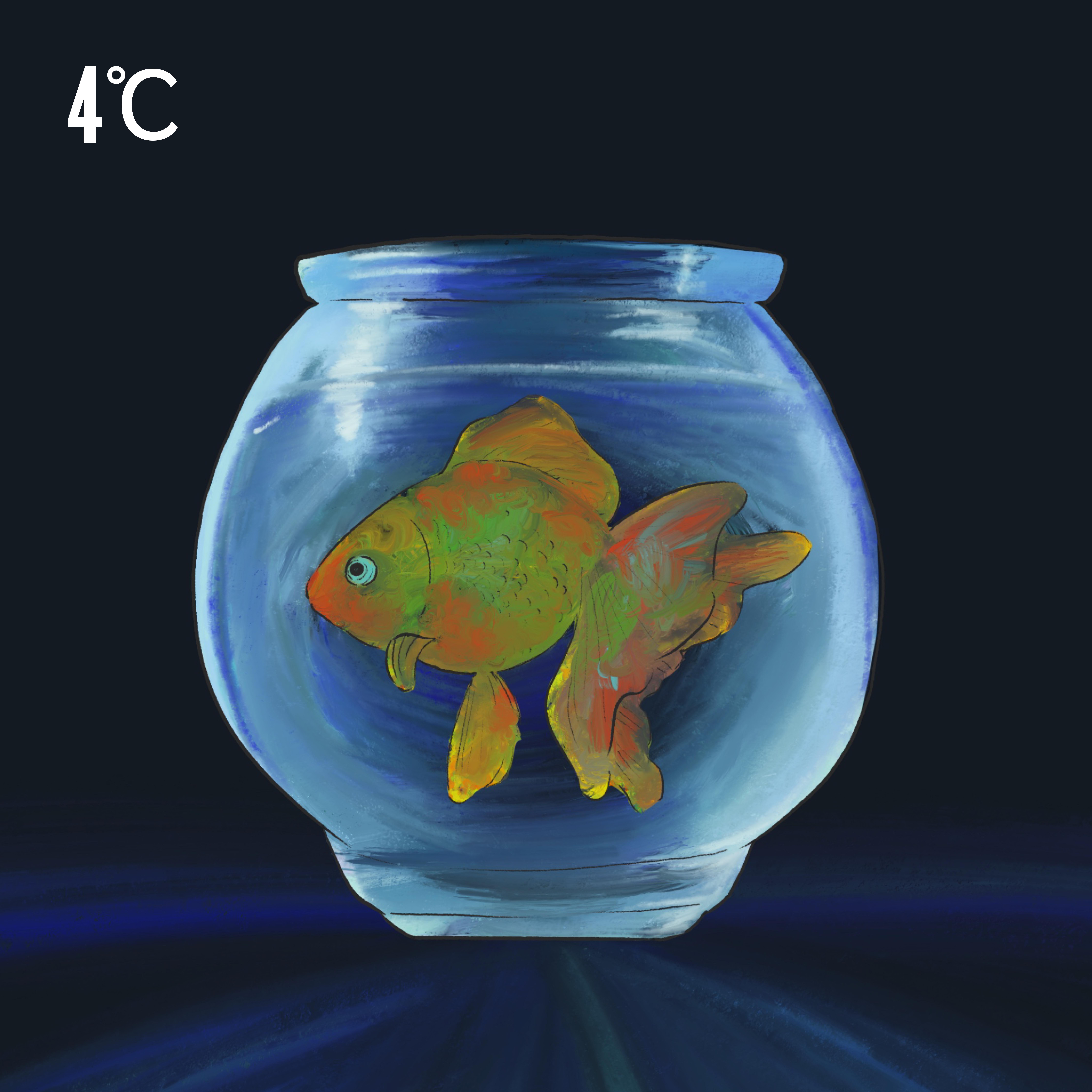未知の箱、コンテンツスタジオの中身はなんだろな

「コンテンツ」という言葉を聞く機会は、2010年代後半から急激に増加した。そうした世の中のコンテンツ全盛時代に合わせ台頭した一つのビジネスモデルである「コンテンツスタジオ」。名前だけが一人歩きしているような印象も受けるこのコンテンツスタジオを解明し、時代の変化の糸口を考える。
目次

コンテンツスタジオとは
コンテンツスタジオとは、その名の通りコンテンツを制作するスタジオのことである。しかしこの言葉が広まるようになったのは、コンテンツスタジオがただ制作のみを行う制作会社の役割を大きく逸脱したことに由来する。別名「ブランドスタジオ」と呼ばれたりもするこのコンテンツスタジオ。
まずはその成り立ちから紐解いていこう。
本来のコンテンツ制作会社が、受注された案件に対して適切なコンテンツ制作を行うために誕生したのに対し、コンテンツスタジオは、メディアのコンテンツ制作部門が独立化する形で誕生した。そして、本来受注したものを生産するだけだったコンテンツスタジオはコンテンツ制作のみならず、メディア事業、企業のブランディング事業をコンテンツ制作を通して行うようになったのだ。
本来、業務を受注される側だったコンテンツスタジオが主導権を持ちあらゆる事業展開を始めるようになったため、ここまで注目されている。
コンテンツスタジオ発生の要因
コンテンツスタジオという名前が各方面に伝わるようになったのは様々な背景がある。
企業は、コンテンツを制作することで自身のブランド価値を高める「ブランデッドコンテンツ」の制作を行うようになり、また、一見広告には見えないが実はプロモーションだったという「ネイティブ広告」の需要が高まった。
広告を見る人が、プロモーション然とした広告に対して耐性がつき嫌気がさし始めた、言い換えれば購買につながらなくなったことで、「純粋に楽しめる、かつついでに企業の名前も知ってね」というコンテンツを軸足に据えた広告に需要が高まった。つまり、コンテンツと広告の融合が進んでいるということだ。
ド派手な広告を、街のどでかい画面や、家にある一番どでかい画面のテレビに映し出せばみんながかじりついて買ってくれる時代は終わってしまった。テレビに出るために、雑誌で紹介してもらうために、お店に置いてもらうためにコンテンツを作る時代の終わり。そして、純粋におもしろいものに人が集まりそこから購買へという流れが出来上がっていった。
その結果、おもしろいコンテンツを作れる人間に一番需要が高まった。そのためコンテンツ側が主導権を持つことが可能になったのだ。おもしろいコンテンツってなんだよという話はあるが、それは永遠の命題でしょう。
メディアが先頭を走り、メディアが一番大事だった時代からコンテンツファーストの時代へ。これが、コンテンツスタジオという名前が広がっている背景であろう。
代表的なコンテンツスタジオ
一口にコンテンツスタジオと言っても形態は様々であり、これがコンテンツスタジオだ、という明確な定義は出来ない。イメージを共有すべく、代表的かつおもしろいコンテンツスタジオを紹介しよう。
VICE
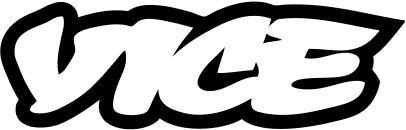
デジタルメディアとして今や世界30か国に支部を持つ「VICE」。VICEは雑誌制作というメディア形態からスタートしたが、ドキュメンタリーなどの映像制作に着手を始める。
VICEのコンテンツ制作部門の手腕の高さが評価され始めたことで、VICEはメディアだけでなく本格的にコンテンツ制作に乗り出す。コンテンツ制作会社「Virtue」を傘下に設立したことで、VICEオリジナルコンテンツの制作と共に、コンテンツの受注委託を行うようになる。それ以降、受注委託と並行してオンラインビデオチャンネル、映画制作、『i-D』というマガジンなど様々なオリジナルコンテンツを提供してきた。
以下は、VICEとVirtue、『i-D』らVICEグループが担当したCHANELのプロモーション動画である。
雑誌というメディア事業から始まった「VICE」だったがメディア事業、コンテンツ事業、ブランド事業、三すくみそろうことでVICEは一介のデジタルメディアからコンテンツスタジオへと変貌していった。
CHOCOLATE INC.

日本において「コンテンツスタジオ」というモデルの先頭を走るのは、2015年に設立された株式会社チョコレイト(CHOCOLATE INC.)だ。
元々、コンテンツ制作会社としてスタートした株式会社チョコレイト。コンテンツ制作に始まり、コンテンツの受注委託も行うことで、徐々にコンテンツスタジオとして成長している。代表の渡辺裕介は以下のように話す。
チョコレイトをコンテンツの会社として本当に大きくしようと考えたとき、(中略)そのための最も良い手段が「受託」だったんです。これらの価値を高めていければ、オリジナルコンテンツを作ることになった際も、予算が十分に割けなくても先に関係性があることで、著名クリエイターが参加してくれたり、クライアントさんがスポンサードしてくれたりと、実現可能性が高まると考えました。
ピュアに「世界一たのしみな会社」を目指すから、気鋭の人材は惹きつけられる──チョコレイト 渡辺裕介×クラシコム 青木耕平 対談前編 by クラシコムジャーナル
受託業務を経て、自主制作できるコンテンツスタジオへの変貌を目論むチョコレイト。以下の動画は、2019年に大バズりし300万回再生を越える(2020年2月時点)Youtuber、あさぎーにょの動画である。あさぎーにょ自身もチョコレイトに参画しており、この動画はチョコレイトのプロデュースによるものだ。
さらに、かるたやスピードと言ったボードゲームの制作、中国で「微電影」と呼ばれるインターネットで発信される映画を作る、微電影レーベル「37.1°」を設立するなどその勢いは着々と大きなものになっている。
ピクサーや任天堂に並ぶ「世界的エンタメ企業」になると宣言するチョコレイト。彼らの足跡を注意深く観察すれば、おもしろいものに出会える可能性は高まるかもしれない。
コンテンツスタジオのおもしろさ
「コンテンツスタジオ」という名前が一人歩きしているが、はっきりとしたモデルが存在するわけではなく形態も様々である。この言葉は「メディアファーストからコンテンツファーストへ」という時代の流れの副産物に過ぎないのかもしれない。
定点で見れば、コンテンツ制作会社が時代と共にその役割を拡大したがために「コンテンツスタジオ」という新しい名前を付与されたに過ぎない。同時に、俯瞰で見ればメディア、ブランド、コンテンツ、その三位一体モデルをコンテンツスタジオと呼ぶことができる。
そしてこの三位一体モデルを考えたときに面白い現象が見えてくる。例えば、VICEの例。
メディア記事にしろ、ドキュメンタリー映像にしろオリジナル番組にしろ、その価値を担保しているのは「VICEっぽさ」である。VICEがやっているならおもしろいはずだ、という雰囲気がVICEのコンテンツスタジオとしての役割を成立させている。
そしてVICEはトピックを見つければ、これは映像の方が映えるから映像で出そう。これは文字媒体で雑誌化も検討しよう、とトピックに合わせて流すチャンネルを選択することができるのだ。
分業制の力関係の変化
メディアに合わせたコンテンツを提供することではなく、まず制作物があることが前提で、それでは制作物の中からどれをどのチャンネルにばら撒くのが適切だろうか。というフェーズに突入した。
多チャンネル化がデフォルトの環境となり、読者・ユーザー・オーディエンスとの接触面を、プラットフォーマー(SNSや動画プラットフォームや各種ストリーミングサービスなど)に奪われている以上、コンテンツメーカーの戦略は、そこと「いかに戦うか」ではなく、「いかにうまく使うか」という戦略へと移り始めている。
来たるべきコンテンツメーカーのかたち:ヒップホップコンテンツのプロ集団〈Mass Appeal〉に日本のメディアやレーベルが学ぶこと(若林恵)by 新しい音楽の学校
コンテンツスタジオはさらに進化し、「コンテンツレーベル」という形態が誕生し始めている。メディア、ブランド、コンテンツ三位一体モデルがコンテンツスタジオだとしたら、その上部構造としてどれをメディアで発信するか、企業と連携するか、映像作品などのコンテンツにするかを選ぶことが出来る、言わば「切り口」だけを提供する存在が「コンテンツレーベル」と言えよう。
テクノロジーからカルチャーまでを通して最先端の未来予測を届けるメディア、WIREDの元編集長である若林恵はコンテンツレーベル「blkswn」を設立した。そしてそんな彼が憧れと公言しているものが「Mass Appeal」という会社である。
Mass appealはメディアとエンターテンインメントを扱うNYに拠点を持つ会社だ。彼らはデジタルメディアの運営からドキュメンタリーや映画の制作、そして音楽制作やPVの企画制作、受注委託までを行う。
そして、そんな彼らが提供するのはhiphopという切り口のみである。
彼らはそもそもがヒップホップ大好き集団だ。そんな会社であれば、つくりたいコンテンツは当然ヒップホップにまつわるものしかない。彼ら自身がヒップホップオーディエンスであるがゆえに、ヒップホップ好きのオーディエンスに刺さるネタや語り口を知り尽くしている。そのスキルセットとネットワークをもってすれば、ことがヒップホップに関わるのであれば、音源開発からPV制作、プロモーションまで一気通貫で行うこともできれば、ドキュメンタリーの制作、ライブの企画、文化施設のコンサルティングまで、あらゆるコンテンツをつくることができる。
来たるべきコンテンツメーカーのかたち:ヒップホップコンテンツのプロ集団〈Mass Appeal〉に日本のメディアやレーベルが学ぶこと(若林恵)by 新しい音楽の学校
コンテンツスタジオに必要なものとは
メディアが主導権を持つ時代が終わり、コンテンツを作る人がメディアに合わせたものを作る必要がなくなっていった。SNSの発達によってテレビやお店に商品を取り上げてもらう必要がなくなり、制作者側が直接「おもしろいものあるからおいでよ!」と呼びかけるスタイルが定着した。そして同時にテレビから多岐に渡るSNSまで、出会いの場が多チャンネル化したことで「おもしろいもの」と「おもしろいものを欲している人」をいかに結びつけるかという新たな機軸が必要になった。
そうした時に、コンテンツスタジオ、コンテンツレーベルに求められるものは、色である。「〇〇っぽさ」がおもしろいものと、おもしろいものを欲している人を結びつける鍵になる。
コンテンツスタジオ、コンテンツレーベルがどうなっていくのか。そしてダンチブロードキャスティングがこれからさらにどんな色になっていくのか。どちらも見逃さないで欲しい。